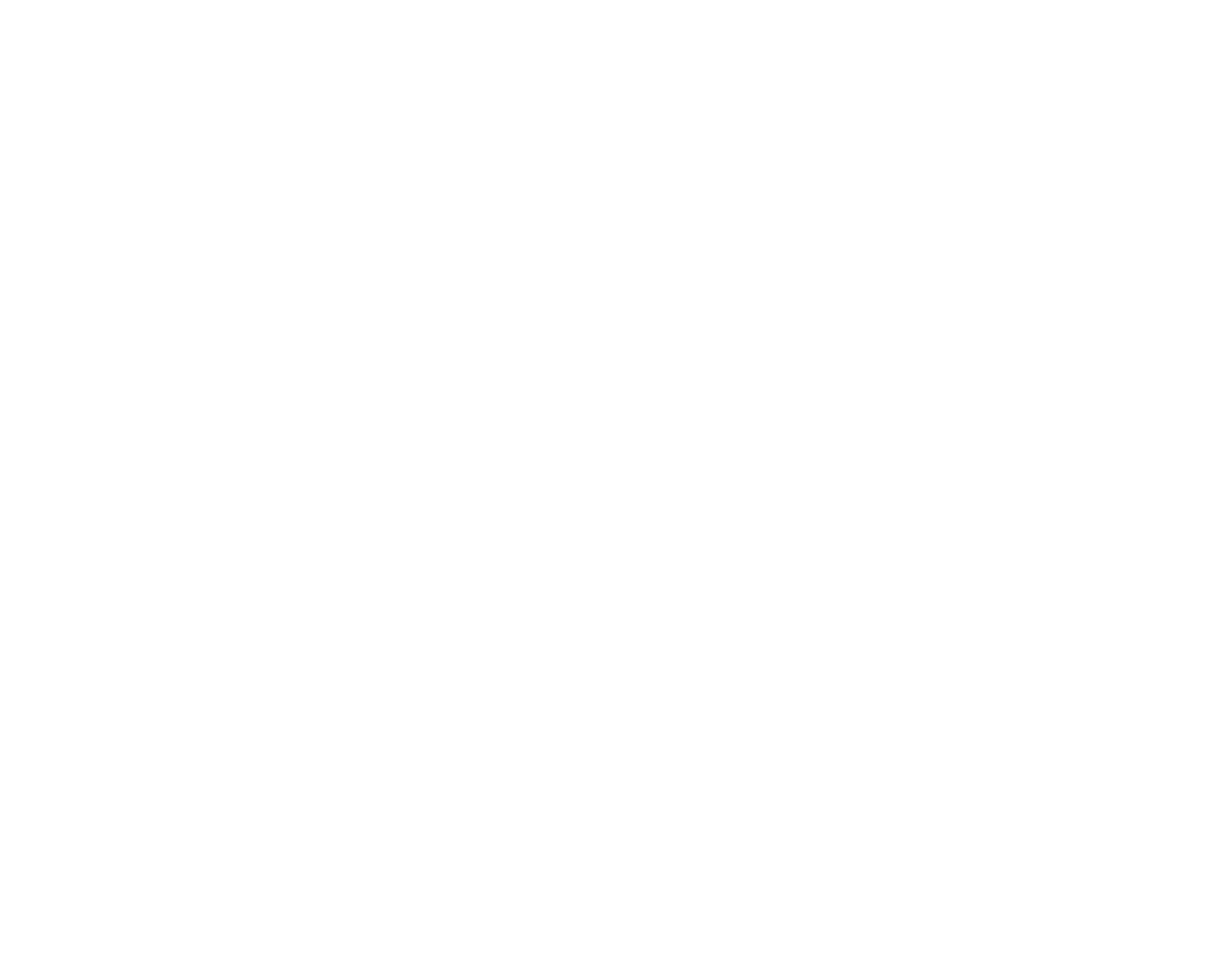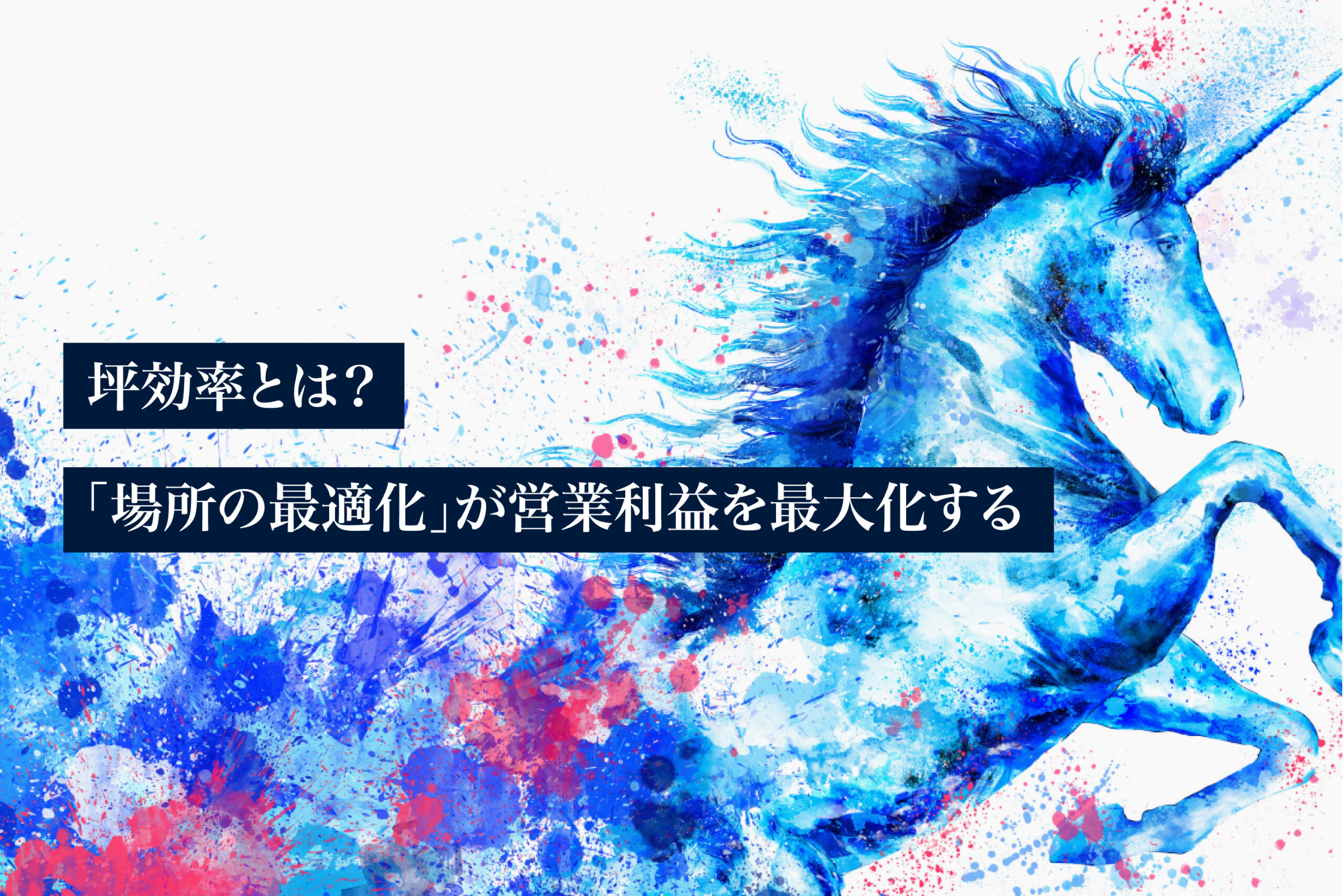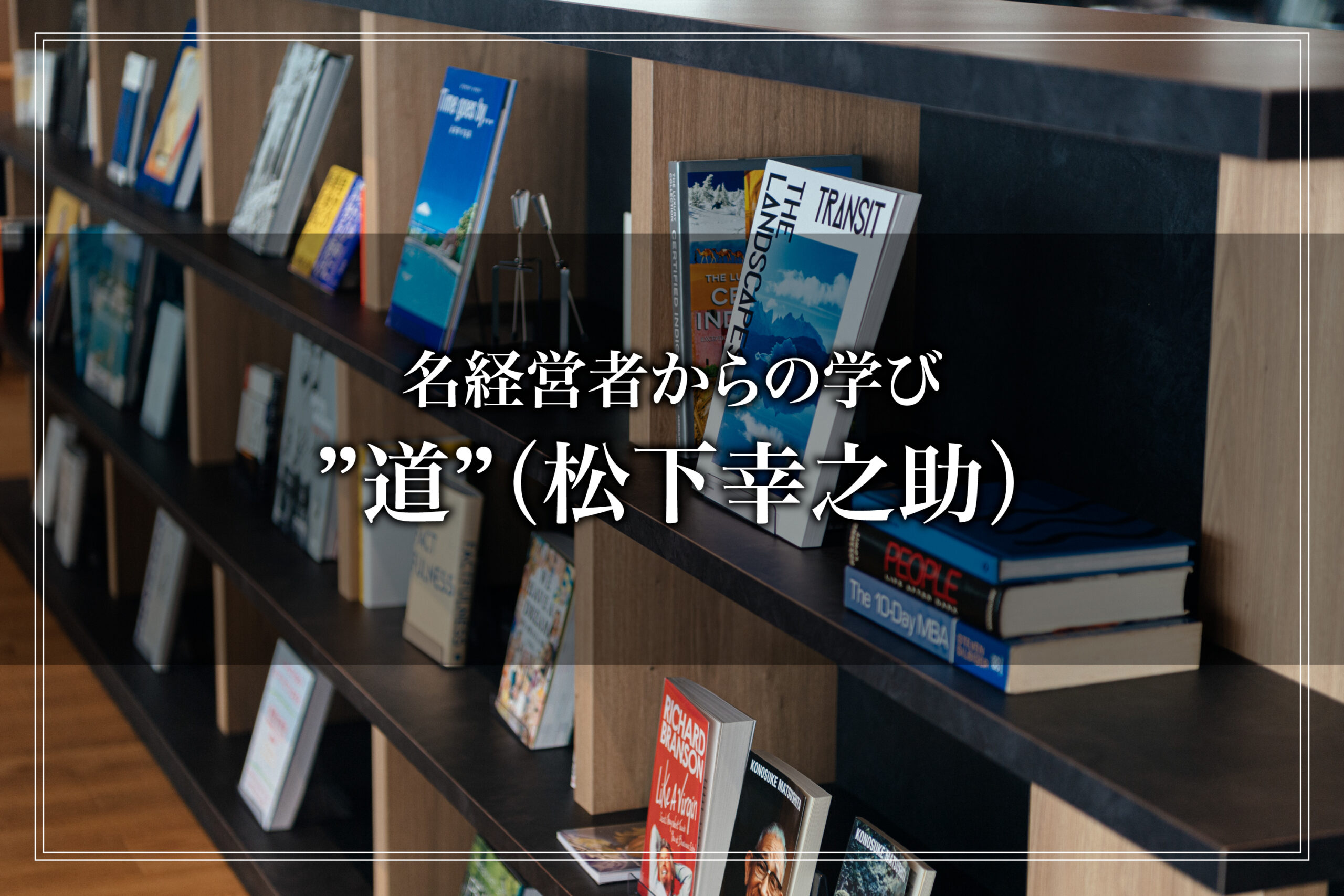ディ・ポップスグループでは、ベンチャーエコシステムを、「共通のアイデンティティと理念の元に集まり、革新性の高い事業モデルにより、社会課題解決に挑戦し続ける企業群の集合体を支える、成長と永続のためのプラットフォームのこと」、と捉えて、その理想の形の実現に向けて日々挑戦と努力を続けています。
以下、ベンチャーエコシステムについて、因数分解して解説してみます。
1. ベンチャー企業とは
コトバンクによれば、以下のように定義されています。
”産業構造の転換期には、産業の主役が交代し、最先端の分野でそれまでなかった新しいビジネスが生まれ、そして新しい市場が作り出される。そんな時代のニーズを背景に、独自の技術や製品で急成長していく企業を「ベンチャー企業」と呼んでいる。”
もう少し広く捉えると、その会社のトップを始め、社員にも挑戦する文化が浸透しており、独自のアイデアや事業モデルで、新しい領域に取り組む企業であれば、起業したてのスタートアップはもちろんのこと、大きく成長しようともそのスピリッツがあればベンチャー企業と言えるのではないでしょうか。
その視点で見れば、例えば国内では、Go Boldをバリューに掲げ、次々と新サービスをリリースしてきたメルカリや、大きく成長した後でも、全く新しい技術による基地局で楽天モバイルを立ち上げた楽天グループなども、ベンチャーと言えます。
また、海外では、アルファベット社にしても、メタ社にしても、未だにベンチャー(ちなみにベンチャーは和製英語と言われています)魂に溢れているのではないでしょうか。
2. センミツとは
不動産業界においては、「商談が成立するのは1000件にせいぜい3つ程しかない」と言われており、そのことを指して”センミツ”と呼ぶそうです。また食品メーカーの業界においては、「1000件企画してもそのうちヒットして生き残るのはせいぜい3商品しかない」と言われており、この業界でも”センミツ”という言葉が使われます。
そして、ベンチャーキャピタル(VC)の業界では、「1000件面談して投資を検討したケースが3%、実際に投資したケースが1/3、無事exitしたケースが3割」という、あるファンドの事例データがあります。1000 x 0.03 x 1/3 x 0.3 = 0.3%、すなわち”センミツ”です。
このように、ベンチャー企業が成功する確率は極めて低いと言えます。
しかし、以下の心掛け次第で、その成功の確率を上げることはできます。
①誰にも負けない努力を継続する。
②同じ立場の仲間との学び合いや助け合いをする。
③相談できる先輩経営者やメンターによる支援を受ける。
④起業や新規事業の成功体験や失敗からの学びを活かす。
3. エコシステム(生態系)とは
ウィキペディアによれば、エコシステムとは生態系の訳で、それは、
”生態系(英: ecosystem)とは、生態学においての、生物群集やそれらをとりまく環境をある程度閉じた系であると見なしたときの呼称である。ある一定の区域に存在する生物と、それを取り巻く非生物的環境をまとめ、ある程度閉じた一つの系と見なすとき、これを生態系と呼ぶ。”
と定義されています。
これをビジネスの世界に反映して捉えるならば、物理的に一定の地域に集まる必要はないものの、一定の共通のアイデンティティと理念を持つ、企業群集と言えます。
ある森を想像した時、そこには種々な植物、その種子を運ぶ昆虫や小動物、それらを捕食する大型の動物らで構成されています。それらが相互に依存し合いながら、そして動物や植物はやがて朽ちて土になり、他者の栄養となるなどして、循環することにより、森は永続し、そして成長します。
この森を企業の集合体に置き換えた時、そして相互に影響し合いながら、成長し、そして永続するグループになることを目指したとき、それらは、ビジネスにおけるエコシステムを表わすのだと思います。
では、ビジネスのエコシステムとは具体的にはどのようなことでしょうか?
4. コラボレーション
エコシステム内の企業同士は、お互いを食い合う敵でも、競合でもありません。良い関係性を持ちながら、お互いにプラスに影響し合う仲間です。
その間では、次のような取り組みが、自然に発生します。
① 顧客開拓
お互いにとっての新規となる法人顧客や消費者顧客を紹介し合ったり、共同で新たな領域を開拓して新規顧客増を図る。(※単にお互いに仕事を発注し合うのではない)
② 協業
企業Aの新規商品やサービスを起業Bの既存の販売チャネルに乗せるなどして、販売の支援をする。その業務提携は、腹のさぐりあいではなく、双方が誠意をもって話し合い、理に適った条件で契約します。
③ 人材交流
CxOやエンジニア、マーケターなど、異なる企業の同じ立場や職種の者同士で人材の交流や情報交換を行い、刺激し合う。グループ内他企業への短期留学や出向、そして、人材の転籍なども含まれます。
④ 新規事業創出
グループ内の事業会社同士での協業や人材交流をしていく中で、様々な刺激を受けた結果、業務の効率化のアイデアや、新規事業創出のアイデア、新商品やサービスが生まれるなど、利益率の向上や、将来の成長の種が撒かれることがあります。
5. 学び合いと助け合い
企業経営は常に順調、順風満帆ということはありません。競合環境や市場の急激な変化などにより、大変厳しい状況に追い込まれることも多々あります。
荒波を乗り越えるには、お互いに学び合い、助け合う必要があります。
① 勉強会
専門性が求められる分野においては、関係会社で集まってお互いに教え合う勉強会を開いたり、グループ各社が集まって外部講師による学びの会を開いたりします。定期または不定期に懇親会を開き、その雑談の中から素晴らしいアイデアが出ることもあります。
② レンタル移籍
経理部門や営業部門など、ノウハウの伝授と吸収目的、また、新ルートや新システムの立ち上げ期など、一時的に企業Aで人員が不足する時に、その時期に人員に余裕がある企業Bから人材を送り、レスキューをすることもあります。企業Bが同じ状況になった時には、企業Aがヘルプ要員を送り込む、”お互い様”な関係が、エコシステム内では成り立ちます。
③ 共同採用活動
多数あるグループ内企業で合同説明会、といった形で、多くの人材を適材適所で採用するといった協業が考えられます。ただし、グループ内各社のアイデンティティと理念が一致している場合にのみ、その理念に共感した候補者が集まり、結果この活動が成り立ちます。
6. エコシステム内の循環
エコシステムの中は同じ規模、同じ業種の会社ばかりが集まっているのではありません。起業したばかりのスタートアップから、歴史ありながらも挑戦を続ける先輩起業まで多岐に渡ります。また前述したように、企業経営は常に順調、順風満帆ということはありません。残念ながら事業を畳まなければならない企業もゼロではありません。
そこで、エコシステムの特徴として、”循環”はとても重要です。
① ベンチャー企業
エコシステムにおける最も重要な役割を担うのが、新たな事業を起こすベンチャー企業です。森における種や卵に例えられます。社内起業や独立により、グループ内で資本関係を持ちつつ、独立することを奨励したり、理念が一致する優秀なベンチャーと出会ったら、出資を行い、グループとの資本関係を持ち、エコシステムに加わってもらいます。
② メンター
エコシステム内には、豊富な知識や経験を持つアドバイザーや顧問団の存在が欠かせません。森に例えれば、豊富な栄養を蓄え、水を供給するような樹齢何百年の大木のようです。長い年月により築かれた人脈のネットワークから顧客候補を紹介したり、事業戦略立案のための壁打ちに付き合ったり、グループ内各社の経営幹部向けに組織論や文化浸透の研修を行ったりします。
起業家にとって、例え誰にも負けない努力をするとしても、誰にも相談せずに単独で経営に取り組むのと、いつでも相談ができるメンターや先輩経営者がいるのとでは、その成功の確度は何倍にも違ってきます。
③ OBの存在
このように切磋琢磨し学び合い、そして支援を受けながら成長するにつれて、やがてグループ内には、上場や前向きな事業譲渡によりexitに成功する経営者も現われます。中には一旦その会社を離れるOBもいます。
しかし、理念が一致していますので、卒業してもOBは共通の仲間です。先ほどの勉強会に講師として登壇してもらったり、一時的な代打経営者として、成績が振るわない企業の再建に取り組んでもらうなどができます。
④ 再生と復活
残念ながら清算を避けられなくなった会社があったとします。しかし、その会社で働いていた社員の中には、どこでも通用する優秀な人もたくさんいます。また、倒産した会社の経営者も、経営には向かないが、リードエンジニアとしては物凄い能力がある人だったのかもしれません。
それらの人材は、役割を変えてグループ内の他企業に転籍したら、凄く貢献してくれるかもしれません。再出発や敗者復活により、エコシステム内の人材がなるべく輝き続ける仕組み、プラットフォームがエコシステムらしさ、と言えるでしょう。
7. ベンチャーエコシステムとは
以上、いくつかに分解して記述したことをまとめると、ベンチャーエコシステムとは、以下のように定義できます。
①挑戦し続けるスピリットがある企業の集合体
②学び合いと助け合いのネットワークが形成されている
③共通の理念の元に集まり同じ方向を向いた人材で構成される
④個々の成長や再生を繰り返しながら全体として成長を続ける
⑤内部から新たなベンチャーが産まれ、外部からも参画し増殖する
⑥環境の変化に対しては、グループ全体で団結して立ち向かう
⑦その集合体の成長を支えるプラットフォームである
「ベンチャーエコシステムとは、共通のアイデンティティと理念の元に集まり、革新性の高い事業モデルにより、社会課題解決に挑戦し続ける企業群の集合体を支える、成長と永続のためのプラットフォームのこと」
と定義できます。
(株)ディ・ポップスグループとそのエコシステムに参加する企業は共に学び合い、助け合いながら、社会になくてはならないプラットフォームとなるべく、日々努力を続けて参ります。
これからもご支援、応援の程よろしくお願いします。
D-POPS GROUP アドバイザー 杉原眼太