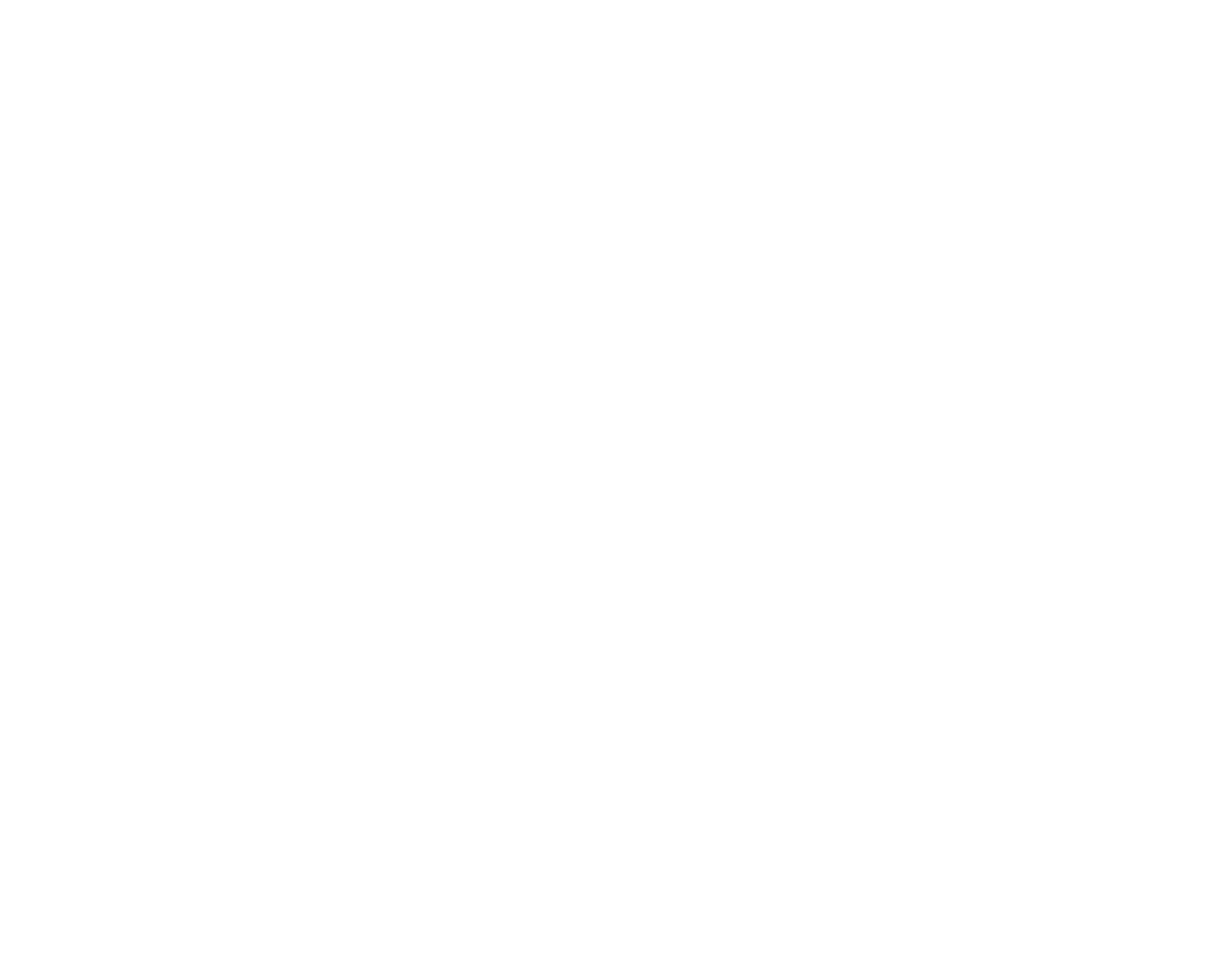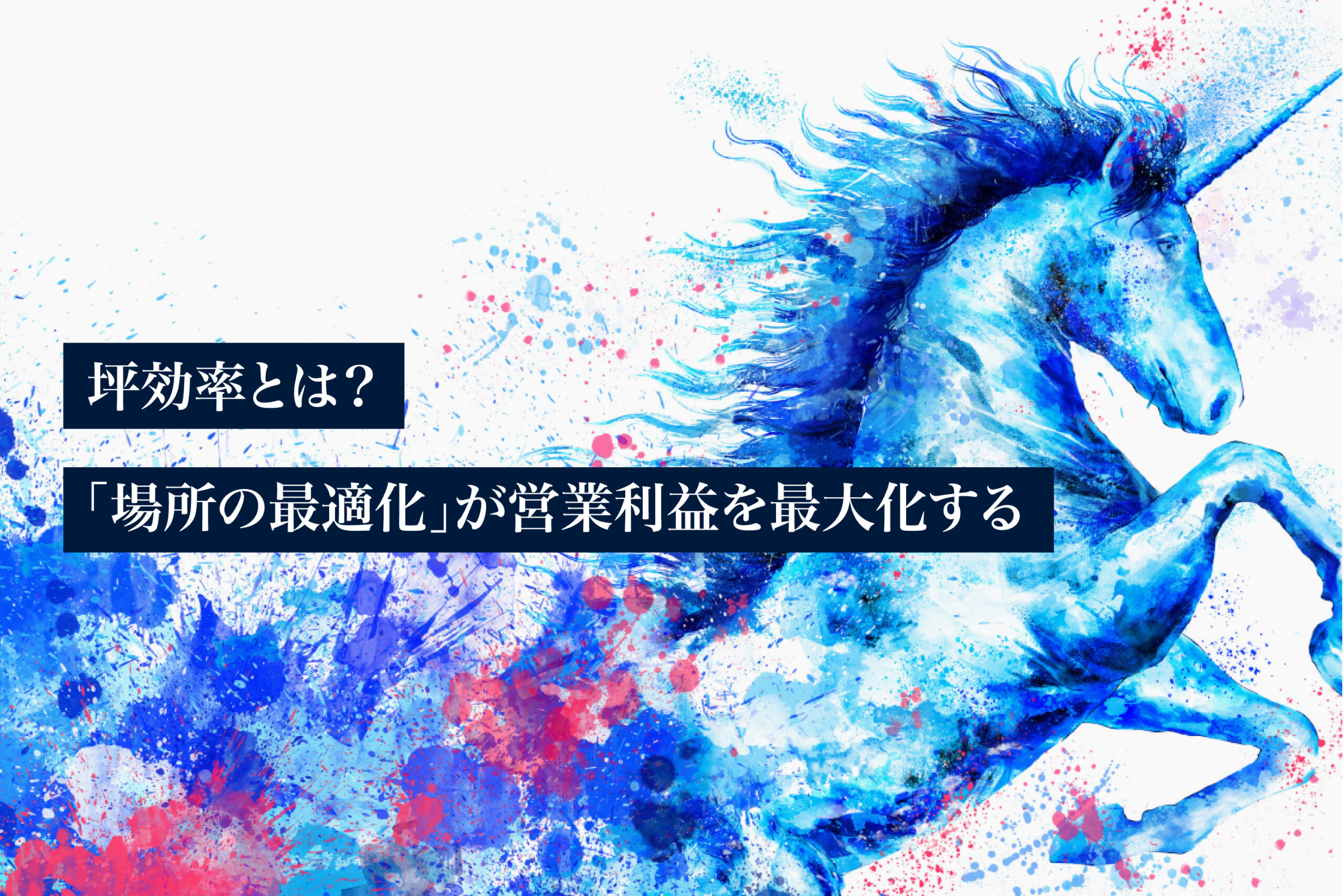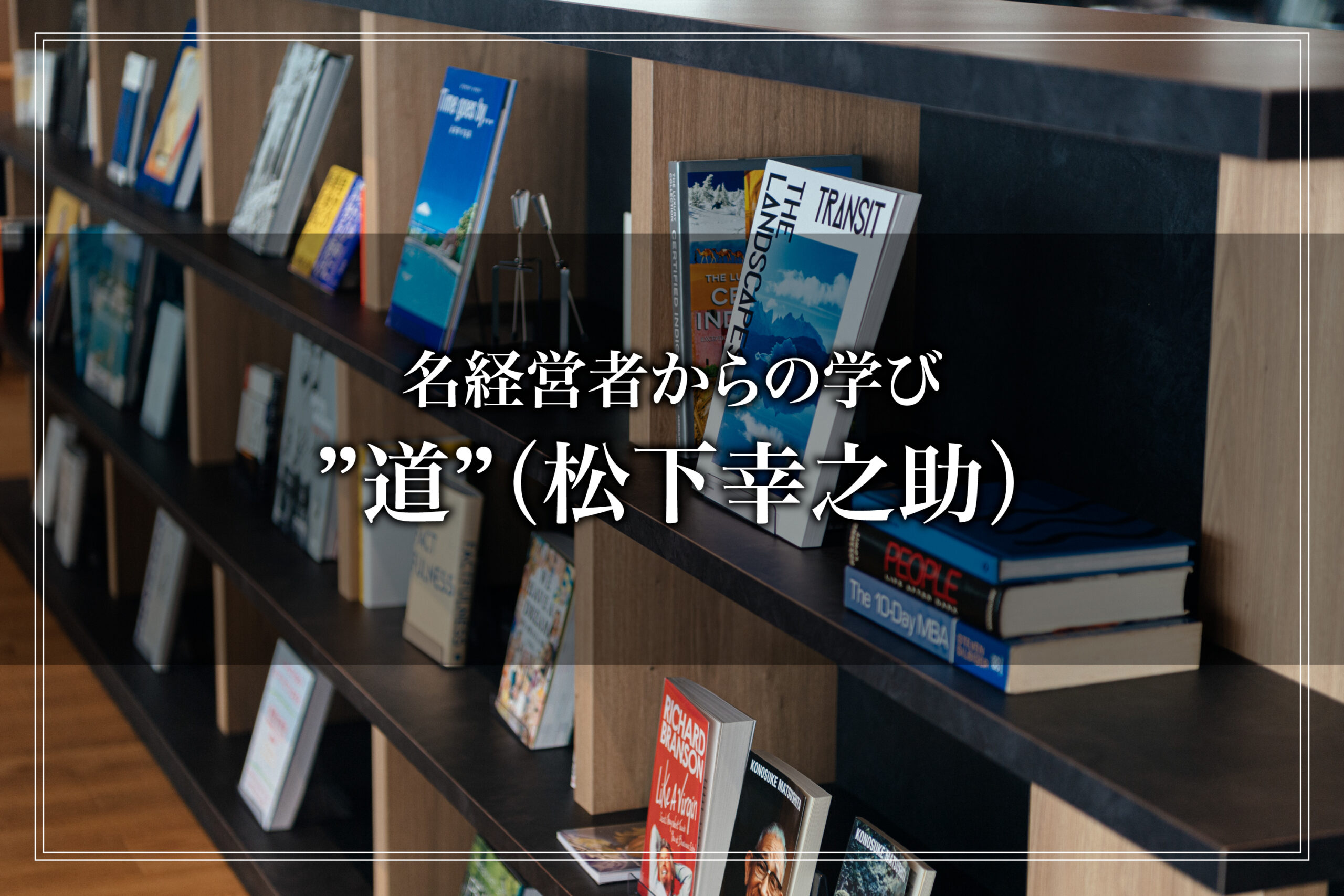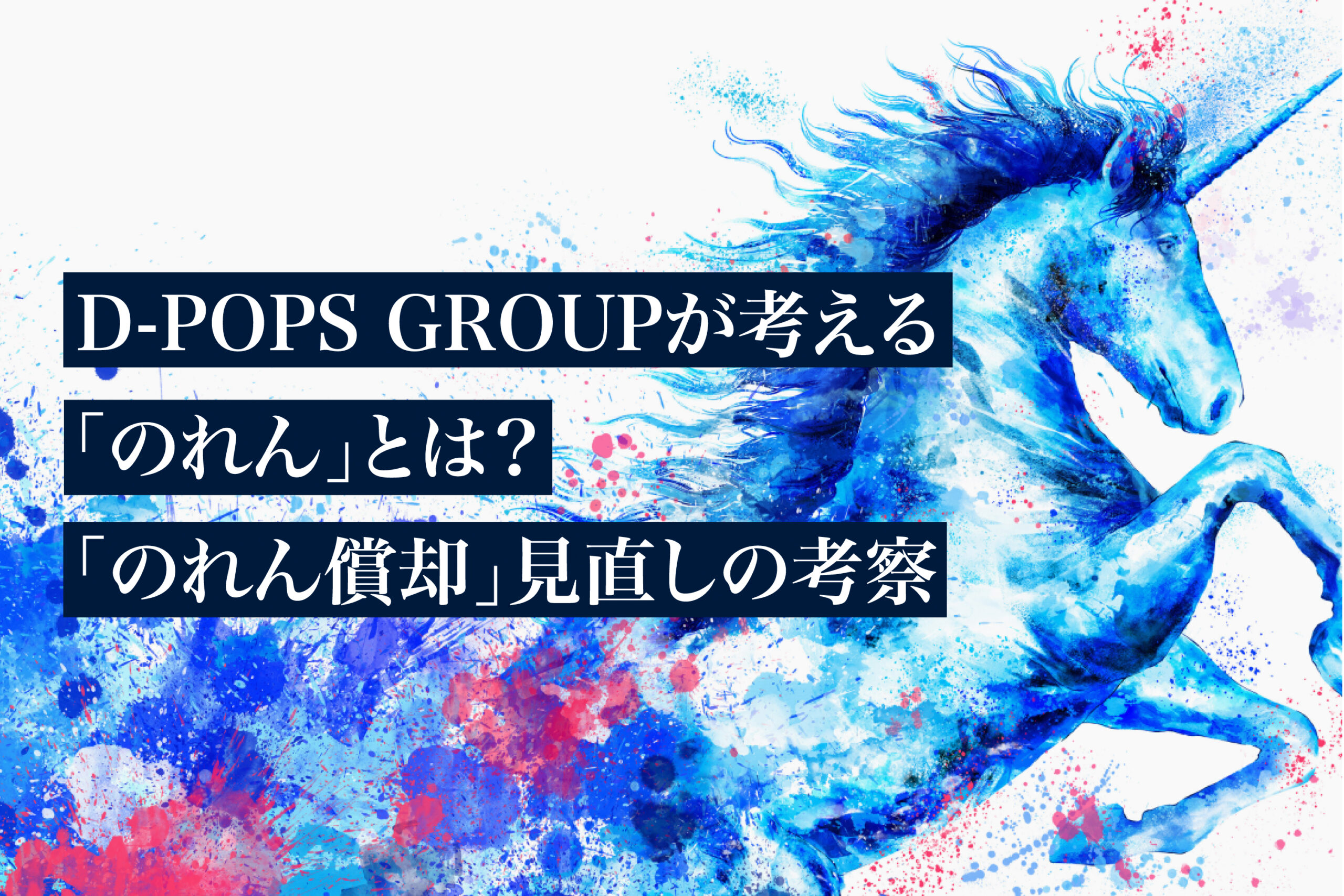
ディ・ポップスグループは、「リアルビジネス × テクノロジー × グループシナジー」を掛け合わせた事業展開をしている会社の集合体で、100年後も社会から必要とされ続けるベンチャーエコシステムの実現を目指しています。また、このベンチャーエコシステムの成長のために、既存事業のオーガニック成長、新規事業・新会社の設立、M&A、CVC、資本業務提携の5つの基本戦略を推進しております。
今回は、この5つの基本戦略の1つである「M&A」と関わりの深い会計における「のれん」について、その会計処理についてニュースとなっていることもあり、取り扱いたいと思います。特に、「のれん」の「非償却」の可能性についても、言及できればと思います。
「のれん」に関しては、2025年5月30日に「のれんの非償却の導入およびのれん償却費計上区分の変更」に関する要望が、日本の会計基準の設定主体であるASBJ(会計基準委員会)にテーマ受付表として提出されました。この要望は、経済同友会、スタートアップ関連13団体、スタートアップ有志35社、企業経営者有志138名の連名で提出され、首相の諮問機関である規制改革推進会議もこれをフォローし、さらにASBJの議論においても、スタートアップ関係者の問題意識が十分くみ取られ、適切な議論が行われるよう、検討プロセスも含めフォローする旨を公表しています。このことは、日経新聞にも「のれん償却の見直し、民間13団体など会計基準機構に提案」という見出しでニュースになりました。
1.「のれんの非償却の導入およびのれん償却費計上区分の変更」の要旨
なお、今回提出された要望の要旨は、以下のとおりです。
①のれんの非償却を導入(選択制)
のれんの償却と併せてのれんの非償却も認める選択制を適用する。
(遅くともスタートアップ育成5か年計画の終期である2027年度までに結論・措置に至るよう検討を要望)
②のれん償却費の計上区分変更
現在、販売費及び一般管理費として営業費用に計上しているのれんの償却費を営業外費用もしくは特別損失に計上する。
(2026年度の結論・措置の可能性も含めて検討を要望)
2.現在の日本の会計基準における「のれん」の定義と取り扱い
現在の日本の会計基準において、M&Aの代金のうち、対象企業の純資産額を上回る金額については、「のれん」として無形固定資産に計上したうえで、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、規則的に償却するとしています。例えば、純資産3億円の対象企業を10億円の代金でM&Aする場合、7億円が「のれん」として無形固定資産となります。またその際に、投資回収期間を7年と想定していたならば、この7億円の「のれん」を毎年1億円づつの定額、7年間で費用化(償却)することになります。
一方で、IFRS(国際会計基準)、米国会計基準においては、「のれん」について規則的な償却は行わず、「のれん」の価値が損なわれた時に減損処理を行う方法が採用されています。これが、今回提出された要望における「のれんの非償却」です。なお、減損処理とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、将来において確実に回収可能な額を除き、資産を費用化することをいいます。先ほどの例でいうと、7億円の無形固定資産が計上されていたが、対象企業が赤字決算続きとなり回復が見込めない場合には、価値が損なわれた、つまり投資額の回収が見込めなくなったとして、7億円の全額を一時に費用化することになります。
これまで、日本の会計基準は、企業の財務報告の透明性と比較可能性の向上を目的として、IFRSとの整合性を目指し基準の改訂を行ってきましたが、このように「のれん」の会計処理についてはIFRSと相違しています。そのため、M&Aを積極的に行っている上場企業では、この相違を理由として、IFRSに移行している企業も多くあると考えられます。IFRSへの移行には、会計コンサルティングの導入、会計監査報酬の増加といった追加コストはあるものの、それを上回るメリットがあると経営判断した上場企業もあるのではないでしょうか。
3.今回提出された要望の背景
政府は2022年に「スタートアップ5カ年計画」を策定していますが、この計画において、M&Aは、スタートアップのエグジット戦略(出口戦略)のみとしてだけではなく、既存の大企業とのオープンイノベーションの推進策として、その重要性について触れられています。(スタートアップを成長させるM&A)
今回提出された要望は、このスタートアップを成長させるM&Aの促進において、日本の会計基準における「のれん」の償却が、阻害要因になっているということを背景としています。すなわち、「のれん」が償却される場合には、営業費用(販売費及び一般管理費)に計上されるため営業利益がのれん償却による費用額の分、減少することとなりますが、これがM&A検討の障害や、M&Aを断念する理由となっているということを背景としています。
特にスタートアップについては、企業価値(M&A代金)に占める純資産額の割合が小さいことが多く、「のれん」は比較的多額となるケースがあります。また、日本の多くの成長企業において、企業価値の源泉であるコアコンピタンスが、人的資本(従業員の知識やスキル、経験)、知識資本(特許、商標、企業ノウハウ)で構成されていることが多いと考えられますが、スタートアップにおいては、その傾向はさらに強いと考えられます。今後ますますAI領域におけるスタートアップの増加が加速すれば、その傾向も加速的に強まっていくと考えられます。
このように人的資本、知識資本は、企業価値の源泉として極めて重要ですが、現在の会計基準では、これらの「自社で生み出された」無形資産は、原則として資産計上することが認められていません。これは、その価値を客観的に測定することが困難であること、また将来の収益の獲得への貢献が不確実であることなどが理由とされています。
このこともあり、非常に価値の高い人的資本、知識資本を有する企業は、企業価値(M&A代金)は高く評価されるものの、会計上の純資産額は小さいというケースが増加していくと考えられます。この結果、これらを対象企業とするM&Aにおいては、「のれん」は多額となっていく可能性は極めて高いと考えられますし、M&Aを行う企業は、その「のれん」の償却により、営業利益も圧迫される可能性も極めて高いと考えられます。
ところで、営業利益は、企業の本業における収益力を示す重要な指標であり、企業価値に大きな影響を与えるものではありますが、「のれん」の償却、非償却による営業利益の増減は、理論的には企業価値に直接的な影響を与えるものではありません。これは、理論的には企業が将来生み出すキャッシュ・フローにより企業価値は評価されますが、「のれん」の償却は現金支出を伴わない営業費用の計上であり、実際の事業活動から生じるキャッシュ・フローには影響しないためです。
それでもなお、「のれん」の償却による営業利益の圧迫が、M&A検討の障害や、M&Aを断念する理由となるのは、営業利益が企業の本業における収益力を示す重要な指標であり、実務においては理論を超えて企業価値評価に大きな影響を与えているということだと思います。
IFRSではこれまで、営業利益の明確な定義がなく、表示も義務付けされていなかったのですが、今後はその定義を明確化して、表示を義務付けすることを検討しています。このことも、営業利益という指標が、実務においては投資家にとって重要な情報であるということを示唆していると思われます。また、日本においては、IFRS適用企業の多くが、「営業利益」あるいはそれに類する項目を損益計算書に表示しています。
4.ベンチャーエコシステムの実現を目指すディ・ポップスグループが考える「のれん」とは
ディ・ポップスグループも、財務状況や経営状況をステークホルダーに説明する義務を果たすうえで、「のれん」の償却、非償却の双方にメリット、デメリットがあることを十分に理解したうえで、「のれん」の非償却、もしくは、その選択制に賛同いたします。ディ・ポップスグループは、ベンチャーエコシステムの実現、成長の戦略の1つとして、M&Aも積極的に行ってきましたが、やはり「のれん」の償却による営業利益の圧迫が、ディ・ポップスグループが実現している企業成長を含めた経営状況の実態を適切に説明する阻害要因になっていると感じているからです。
また、「のれん」を償却する場合には、決算期ごとに「のれん」の額は償却により減少していきますが、一方で営業利益が圧迫されることにより純資産額の積み上げは少額となります。一方で、「のれん」を非償却とする場合には、減損処理を行うような経営状況にさえならなければ、「のれん」は多額のままとなり総資産額も多額となりますが、営業利益は圧迫されないため純資産額の積み上げも早くなります。
財務状況を表す貸借対照表における資産の本質は、平易にいうと、「企業が現在持っている、将来の稼ぐ力のもとになるもの」であり、そして、純資産額は、株主からの出資を除くと、「企業が獲得した利益の蓄積」を表していると考えます。
ディ・ポップスグループにおいては、M&Aでグループ企業としてベンチャーエコシステムに参画してもらう際には、投資額よりも多く将来の稼ぎ、つまり投資回収としてのキャッシュ・フローをもたらすことに確信をもっています。それは、戦略の1つであるコングロマリット・プレミアムによるグループシナジーがあるからであり、そして、ベンチャーエコシステムという共存共栄関係のなかでの事業成長により、このキャッシュ・フローが年々増加していくことを目指しています。
そのため、「のれん」が多額となったとしても、それは、M&A投資による将来の稼ぐ力を適切に表し、そのM&Aの投資回収が純資産の積み上げとなることは、獲得した利益の蓄積を適切に表すと考えるため、財務状況のステークホルダーへの説明においても適切であると考えます。
最後に、ディ・ポップスグループでは、M&Aを行う際に優れたビジネスモデルに着目する場合もありますが、多くの場合には優れた経営戦略を着実に実行する経営者の能力、ノウハウにより重点をおいています。これはディ・ポップスグループが目指すベンチャーエコシステムが、自立支援を重視し、独立した経営者集団であることを目指していることと関連しています。
つまり、コングロマリットプレミアムなビジネス環境を提供し、グループシナジーのなかで更なる自社の成長を望む経営者のためのエコシステムであり、そのため、基本的にはグループジョイン後も継続して自社の経営、成長にリードしていただきたいと考えています。
このような経営者が創ってきた企業は、ディ・ポップスグループにジョインする段階で、研究開発費、人材育成費、マーケティング投資など、将来の収益拡大や競争優位性の構築を目指すための戦略的な投資により、非常に価値の高い人的資本、知識資本が構築されています。
資産の本質は、「企業が現在持っている、将来の稼ぐ力のもとになるもの」であり、画期的な技術を開発するための研究開発費や、優秀な人材を育成するための研修費も、将来の収益増加に貢献するはずであるのに、前述のように、これらの「自社で生み出された」無形資産は、原則として資産計上することが認められていません。このことは、特に無形資産が企業価値の大部分を占める現代の知識集約型社会において、企業の財務諸表がその企業の真の価値や投資の実態を十分に反映していないという課題を生んでいると考えます。
このような状況下で、M&Aによってグループ参画した企業の「のれん」を償却することは、ある種の二重費用計上のような側面を持つ可能性があると考えています。なぜならば、「のれん」の大部分は、グループ企業が過去に人的資本や知識資本に投じた費用、「将来の企業成長のための投資となる費用」であり、資産として計上されなかったものが、M&Aによってようやく「のれん」という形で資産計上されたものと考えられるからです。つまり、過去に一度費用として処理された投資が、「のれん」の償却で再度費用となりかねないという問題があります。
これまで述べてきたように、ベンチャーエコシステムの実現を目指すディ・ポップスグループにとって、「のれん」の大部分の本質は、人的資本、知識資本であり、コングロマリットプレミアムのコアとなる重要な資産であると考えています。そして、これがグループシナジーに拍車をかけ、エコシステム内により多くのキャッシュ・フローが創出され、それがまた将来のエコシステムの成長のために投資されていくという好循環を生み出すことでイノベーションを加速し、日本の未来に貢献したいと考えています。
東京証券取引所のグロース市場の見直しにより、M&Aは、成長戦略の重要な柱として、エグジット戦略の1つとして、その重要性はますます高まっていくと考えられます。「M&A」と関わりの深い「のれん」の会計処理について、これから行われるASBJの検討内容に注目していきたいと思います。
これからもご支援、応援の程よろしくお願いします。
D-POPS GROUP 執行役員 公認会計士 米谷好弘