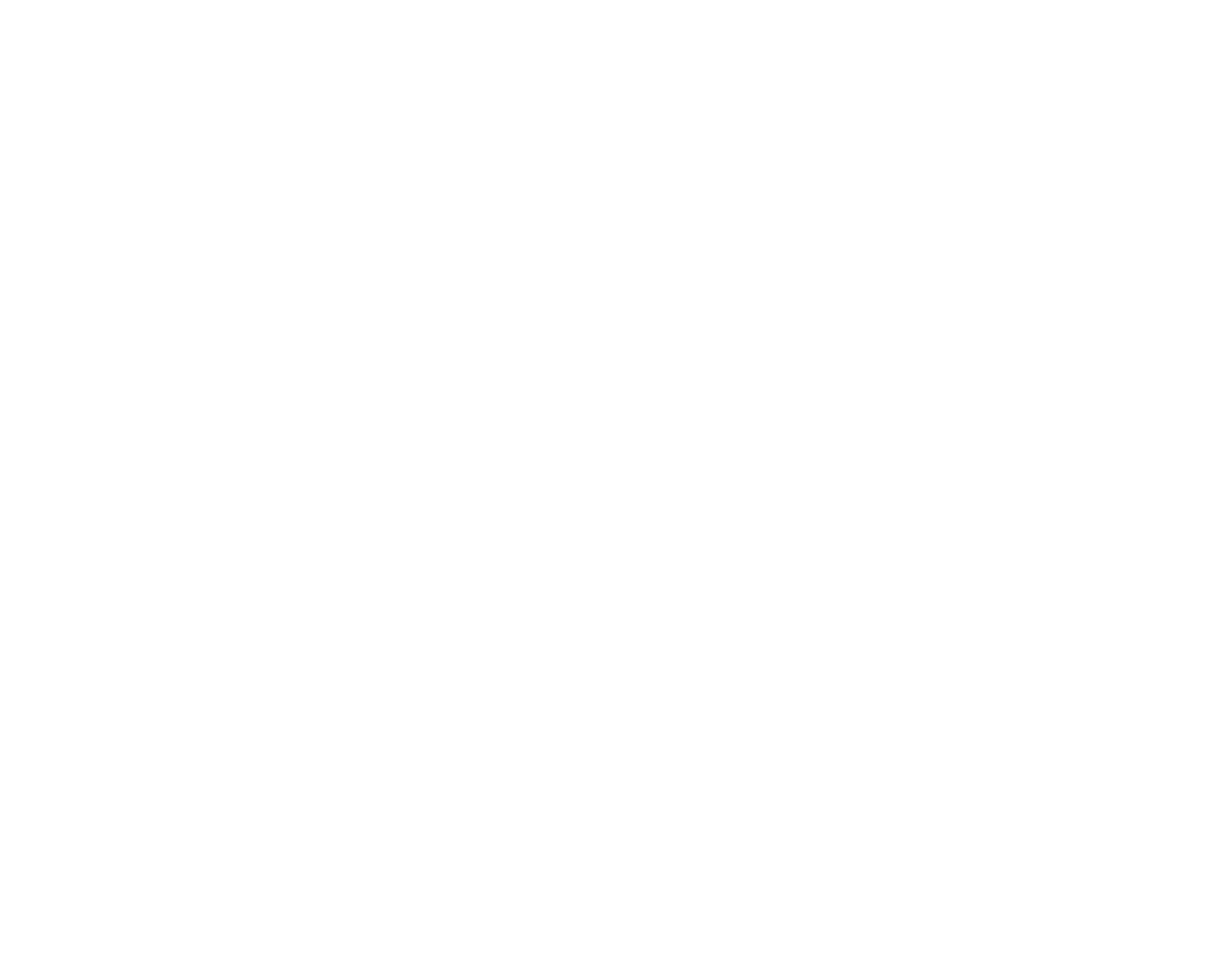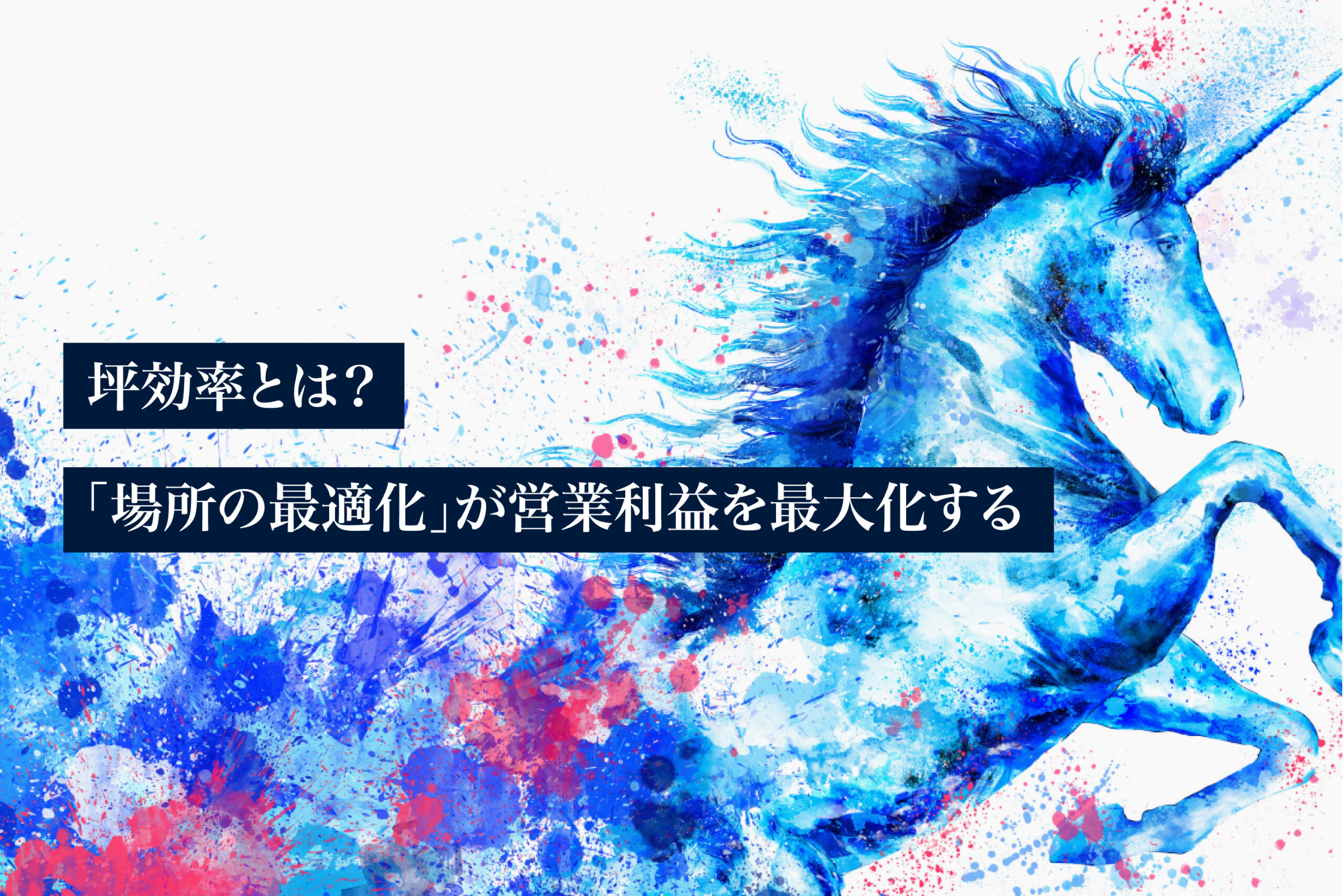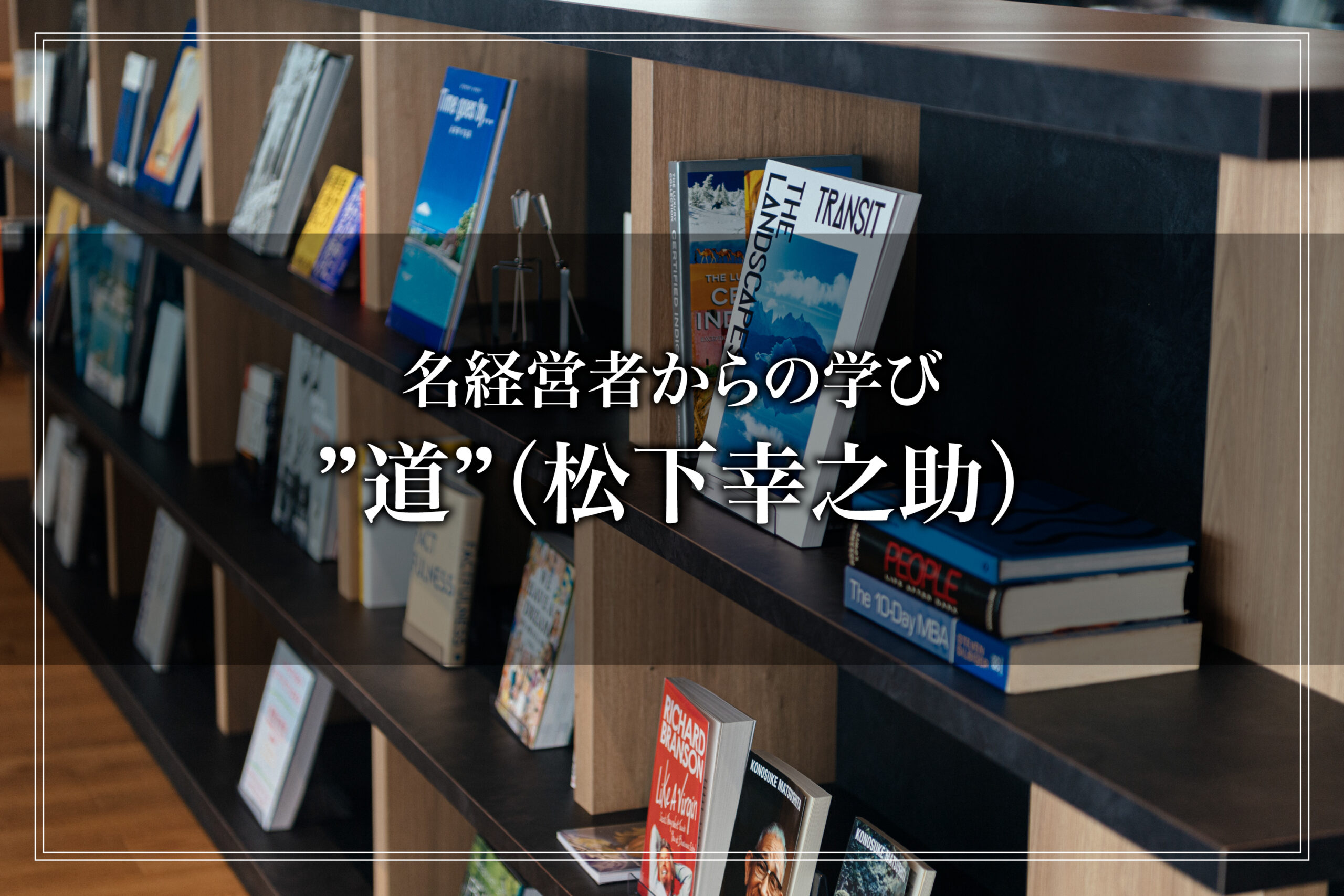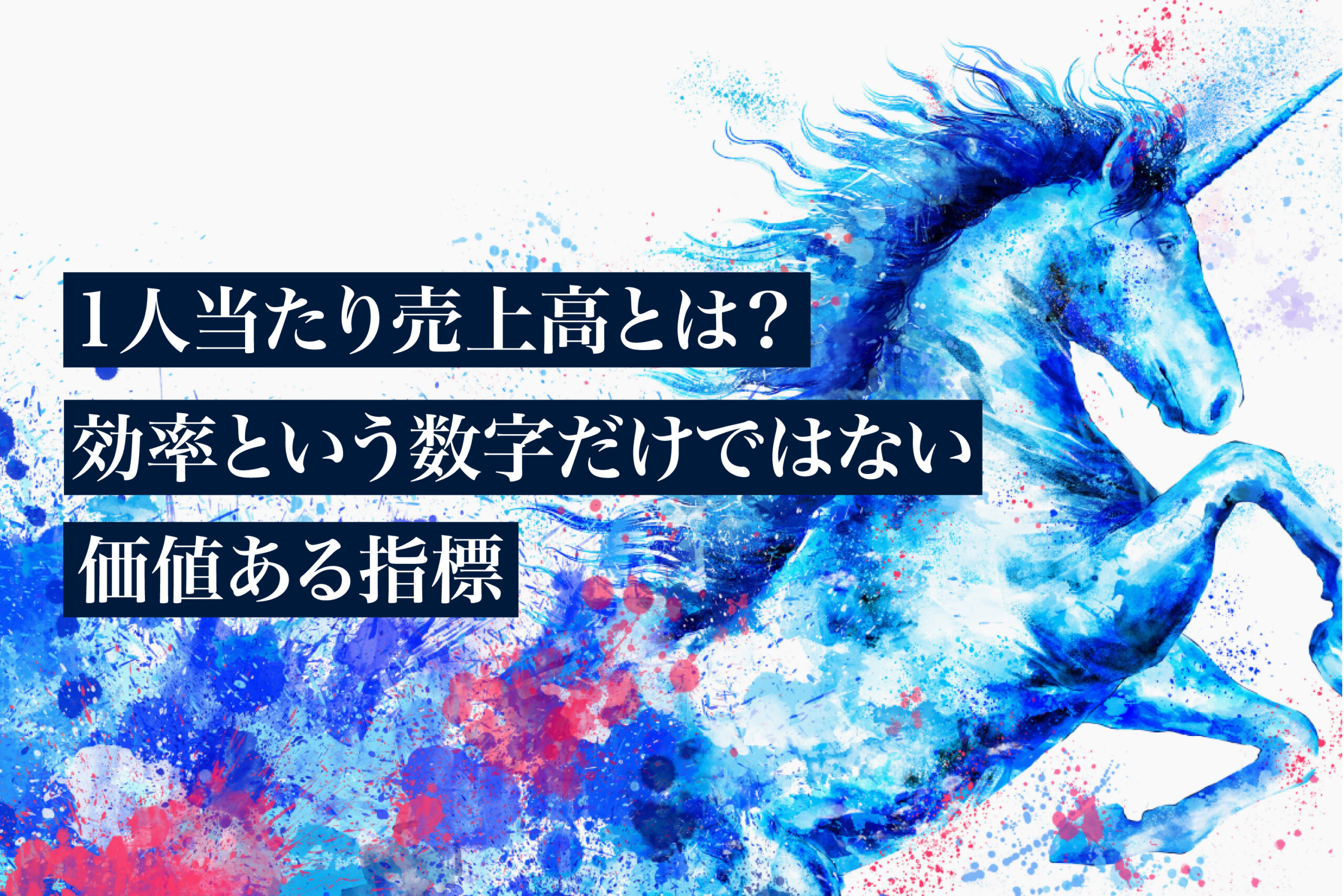
ディ・ポップスグループは、「リアルビジネス × テクノロジー × グループシナジー」を掛け合わせた事業展開をしている会社の集合体で、100年後も社会から必要とされ続ける「ベンチャーエコシステムの実現」を目指しています。今回は、会社経営として必須の生産性や効率性を測る上で非常に重要なポイントとなる「一人当たり売上高」について解説してまいります。
「一人当たり売上高」は業態により大きく異なり、小売店や飲食店といったリアルビジネスやSES/一般派遣等の派遣ビジネスの様な労働集約型の業態では低くなりますし、設備等に投資をする資本集約型のビジネスや、高度なスキルや知識を集めた知識集約型のビジネスになれば高くなりますので、業態を超えた比較だと業態の違いだから致し方ないという結論になりかねないため、今回は同業態での比較を行うことかつ、前回「在庫回転率」の話をしましたので、話に継続性がでる小売業に再度スポットをあて解説していきたいと思います。
1.PL改善の差別化を図る重要ポイント
前回は小売業を経営する上で大切にするポイントとして「在庫回転率」を例に取りました。「在庫回転率」はCFやBSに効いてくるものですが、今回取り上げる「一人当たり売上高」は結果的に数字上では営業利益つまりPLに効いてくる指標です。売上高、利益率、販売点数、販売単価等PLに効いてくる指標は沢山ありますが、なぜ「一人当たり売上高」が重要か、以下順をおってご説明いたします。
2.一人当たり売上高とは
まず、一人当たり売上高とは、従業員1人当たりの生産性や効率性を測るための指標で限界値はありますが一人当たり売上高が高ければ高いほど良いとされます。一般的には年間の売上高を従業員数で割った計算式により算出されます。
例えば
年間4,000億円の売上高の会社で従業員が2,000人いれば、一人当たり売上高は2億円
年間400億円の売上高の会社で従業員が1,000人がいれば、一人当たり売上高は4千万円
となります。
今回例にとる小売業であれば約2,000万円が平均とされ、企業全体だと約3,800万円が平均とされています。
3.なぜ一人当たり売上高が重要か?
一人当たり売上高がなぜ重要か、以下の例を元に解説してみたいと思います。
扱い商品や規模が違う会社同士は比較の結果がわかりづらくなる為、前回の「在庫回転率」の時と同様に、同じ商品を販売していて、売上規模が同程度の家電販売店をモデルケースに解説していきたいと思います。(モデルケースの会社は架空の会社ですが、実際の会社がベースとなっております)
【モデルケース】
①家電量販店B社
店舗数24店 従業員数5,000人 一人当たり売上高1.4憶
売上高7,500億円、経常利益600億円、経常利益率8%
②家電販売店C社
店舗数270店 従業員数11,500人 一人当たり売上高8,000万円
売上高9,000億円、経常利益260億円、経常利益率2.9%
今回モデルケースとして採用したB社は前回の「在庫回転率」で取り上げたB社と同じ会社(数字を最新のものに更新しました)、C社はB社のライバル会社として知られる会社です。
B社は都市型、C社は都市型と郊外型のミックスの会社で、主な違いは出店戦略の違いによる店舗数となりますが、今回見比べていただきたいポイントは従業員数と一人当たり売上高です。B社は7,500億円程度の売上を作る為に従業員を5,000人雇用し、C社は9,000億円程度の売上を作る為に従業員を11,500人雇用しています。年間の一人当たり売上高に換算するとB社は1.4億円、C社は8,000万円で従業員一人当たりの売上が年間6,000万円も違います。
この一人当たり売上高の差が人件費に直結しており、家電量販店の給与平均は大体どの会社も500万円程度のため、1人当り月の人件費を40万円と仮定し比較すると、B社では月の人件費総額が20億円、C社では月の人件費総額が46億円になり、月の差額で26億円も違います。この差を単純に年間にすると312億円になります。B社とC社の経常利益が340億円、経常利益率で5.1%の差がありますが、この差の大きな要因の1つが一人当たり売上高の差からくる人件費であることは明確かと思います。
ちなみに売上規模が違うため一人当たり売上高をベースに同じ規模として比較すると、C社の一人当たり売上高で従業員がB社同様5,000人の場合には、C社は売上4,000億円程度、経常利益率が同様とすると経常利益が116億円程度の会社でB社との経常利益の差は年間480億円ということになります。
また、C社が7,500億円の売り上げを作る場合で比較すると、従業員数は約9,400人必要で、B社とは4,400人差があり、月の人件費を40万円としたときのC社の月の人件費総額は約37億、B社との差は17億円にもなります。年間にすると204億円です。この差がどれだけ大きいかということがお分かりいただけると思います。
前回の「在庫回転率」の時もお話ししましたが、多少の違いはあれど、同じ商品を扱っている家電販売店業界ではB社、C社以外をみても売上総利益率は大体30%程度で、どの会社も同じような水準です。他の業態もそうかとおもいますが、同じ商品を扱っている業態で同じような売上規模だと売上総利益率に大きな差は出にくいと思います。
今回のB社、C社の比較の場合で、C社の売上をB社と同じ7,500億円と仮定した場合の人件費差額年間204億円は、売上総利益率に換算すると3%に相当します。同じものを販売する同業界、売上規模も同程度の会社間では売上総利益率で3%も差をつけるのはものすごく大変なことではないかと思います。
今回もわかりやすい例として一人当たり売上高を、同じ商品を販売していて、売上規模が同程度の家電販売店をモデルケースとして解説いたしましたが、同業界の競合他社とこれだけの経営効率の差は他の指標ではなかなか出ないと考えます。
今回のモデルケースの様な労働集約型のビジネスだけでなく、商品やノウハウで差別化ができる資本集約型や、知識集約型のビジネスでも、従業員を雇用する限り、従業員一人当たりの効率(一人当たり売上高)から逃げることはできません。業界水準を大きく上回る一人当たり売上高を実現することができれば、ビジネスをする上で避けて通れない競合他社との競争上において、大きなアドバンテージを持つことに直結していきます。
4.一人当たり売上高の上げ方
一人当たり売上高の重要性はご認識いただけたかと思いますので、一人当たり売上高を如何に上げるか?というお話をさせていただきます。
単純に人を減らせば一人当たり売上高が上がるのか?というと当たり前ですがそうではありません。一人当たり売上高が上がる会社としての仕組みが確立されていないと一人当たり売上高は上がりません。それどころか会社のサービスレベルが大きく低下し、会社存続の危機になりかねません。
一人当たり売上高が上がる会社としての仕組みは会社によりいろいろありますが、モデルケースとした小売業の例で見れば、出店リスクの少ない売上の小さな小型店を大量に出店するのではなく、売上の大きい大型店中心の出店戦略や、他社に先駆けECに傾注する戦略、物流網に投資による入出荷の効率化、テクノロジーの導入による仕入れ部門や経理部門等の間接部門の超スリム化、そして最大のポイントは一人当たり売上高の重要性の教育が従業員になされており、常に会社と従業員が生産性を高めるための創意工夫をし続ける血の通った経営をしていることかと思います。
経営効率を飛躍的に向上させる一人当たり売上高を向上させるには、ヒト×テクノロジー×経営戦略の掛け算の上に成り立つということになると思います。
5.まとめ
今回も、小売業をモデルケースに一人当たり売上高のお話をさせていただきました。例に出した小売業を含むリアルビジネスの様な労働集約型のビジネスだけでなく、資本集約型や知識集約型のビジネスでもビジネスはヒトにより成り立っています。このヒトの最適化こそが、一人当たり売上高として数値化され、特に労働集約型のビジネスでは、営業利益の最大化につながり、大きな競合他社とのアドバンテージポイントになります。
また、現在は人的資本経営という考え方が多くの会社に根付き、企業価値向上の為の経営手法としてディファクトスタンダードの1つになっています。この経営手法は会社と従業員が生産性を高めるための創意工夫をし続け、成長し続けることにポイントがあると思います。
つまりは、「一人当たり売上高」を追求することは、数字上の経営効率による企業価値向上と効率と、数字ではない人的資本経営による企業価値向上という両面の価値があると考えます。
繰り返しですが、ビジネスはヒトにより成り立っています。経営戦略を考えるのも、実行するのも、テクノロジーを使うのもすべてはヒトであります。その為に必要なものが、ヒト×テクノロジー×経営戦略の掛け算であると、ディ・ポップスグループは考えます。
その考えの元、ヒトが輝くため、また社会課題解決のために、ベンチャー企業に対して、出資を通じた支援と、効率という数字だけではない価値を通じたグループエコシステムの実現を目指しています。
これからもご支援、応援の程よろしくお願いします。
D-POPS GROUP 常務執行役員 渡辺哲也
☆「在庫回転率」に関する考え方についての記事も、参考までにぜひご一読ください。
https://d-pops-group.co.jp/column/inventory-turnover/